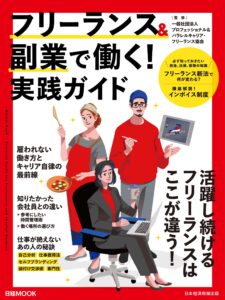『外資系トップコンサルの聞く技術』文庫版が出版されました
2014年出版の『外資系コンサルに学ぶ聞き方の教科書』の文庫版が、三笠書房発売になりました。
もともと東洋経済新報社から出版した単行本に文庫化のオファーをいただき、実現しました。
初の文庫化です。
ぜひ書店でお手に取ってご覧ください。
文庫化にあたり、今の状況を鑑みてあとがきを書き直しました。
以下、掲載いたします。
—–<以下、あとがき>——-
おわりに - 今こそ「聞く力」が求められている –
今から10年近く前のことです。娘が小学校に入学するので、学校に入るまでに身につけておくべきことは何かを数人の先生に聞いたところ、ある先生から以下のことを言われました。
「人の話を聞けるようにしておいてください。人の話を聞くとは、大人しく従順に言うことに従うという意味ではありません。相手が何を言っているのかを最後まで聞いて、素直な心でそれを受け取り、理解した上で、行動に移せることです。最近の子供は、最後まで話を聞かずに、相手が話している間にかぶせて話し始めてしまいます。それは礼儀に欠けるからいけないということだけではありません。人が話している間も自分が何を話そうかを考えているため、理解力が伸びず、結果的に学力も低くなります」
てっきり、「自分のことは自分でできるようにしておく」などと言われることを想定していたので、この話は意外でした。しかし、考えてみれば学問とは対話です。国語でも算数でも問題文の理解ができなければ、スタートラインに立てないというのは納得が行きます。そして、日常や我が身を振り返ってみれば、人の話を聞いていないのは、子供よりもむしろ大人なのかもしれないとも思いました。
話はややそれますが、インターネット、SNSではささいな言葉尻を捉えて議論が炎上したり、キャッチーなニュースに振り回されたりということが頻繁に起きています。これも断片情報だけを聞きかじって鵜呑みにしたり、思い込みで聞いてしまうなど、聞く力が足りないために起きている反応とも言えるのではないでしょうか?
今、私たちはコロナ禍の中での紛争や戦争で、とても不安な状況に陥っています。ちなみに「戦争」の反意語は何だと思いますか? よく言われるのは「平和」ですが、私はそうではないと考えています。戦争とは手段であり、平和とは状態を表す言葉だからです。よって戦争の反対の言葉は何かと考えると「対話」なのではないでしょうか。対話が上手くいかないために対立が生まれ、戦いという手段を用いてしまうのだと思います。
そう考えると私たちが聞く力を少し意識して発揮するだけで、相互理解が深まり、平和にも繋がるのかもしれないという希望を持ち、私も大切な人たちの声、そして自分の心の声をきちんと聞けるよう精進し続けることをここに誓い、筆を置きたいと思います。
最後になりましたが、いつも言葉の足りない私の話を温かく聞いてくれる家族、話を聞いて勇気づけてくれる友人、講演で私の話を熱心に聞いてくださる皆様、そして、本書を手にとっていただいた皆様に心から感謝いたします。
清水久三子